2025.07.31 今月のおすすめ書籍(2025年8月)
おすすめ新刊紹介「文庫」
植物少女
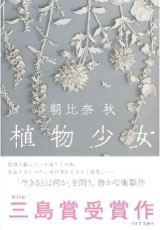
| 出版社 | 朝日新聞出版 |
|---|---|
| 発刊日付 | 2025年8月7日 |
| 著者 | 朝比奈秋 |
| 本体価格 | 836円(本体760円+税) |
| ISBN | 9784022652041 |
静かに生きて考える
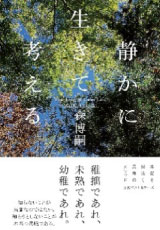
| 出版社 | ベストセラーズ |
|---|---|
| 発刊日付 | 2025年8月18日 |
| 著者 | 森博嗣 |
| 本体価格 | 1,320円(本体1,200円+税) |
| ISBN | 9784584394045 |
おすすめ新刊紹介「新書」
あなたが政治について語る時
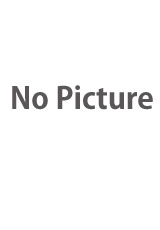
| 出版社 | 岩波書店 |
|---|---|
| 発刊日付 | 2025年8月22日 |
| 著者 | 平野 啓一郎 |
| 本体価格 | 1,110円(本体1,000円+税) |
| ISBN | 9784004320760 |
おすすめ新刊紹介「一般書」
言葉のトランジット

| 出版社 | 新潮社 |
|---|---|
| 発刊日付 | 2025年8月 |
| 著者 | グレゴリー・ケズナジャット |
| 本体価格 | 1,650円(本体1,500円+税) |
| ISBN | 9784065404263 |
旅に出かけ、見えてきた景色。
2つのレンズを使って英語と日本語の間を行き来する、芥川賞候補作家の初エッセイ集。
+*+*+*+*+*+*+*+*+*
英語を母語としながら、日本語で創作する著者だからこそ見えてくる24の景色
「俺を使わない僕」・・・相手との距離で変わる日本語の〈一人称〉の不思議とは?
「轍」・・・英語と日本語の相互作用が創作に与える影響とは?
「言葉の出島」・・・日本にいながら英語を期待されるプレッシャーとは?
「マイジャパン症候群」・・・日本在住の英語話者コミュニティー独特の症状とは?
「Because Plants Die」・・・この英語、ちょっとおかしい? 言葉が持つニュアンスとは?
and more…
おすすめ新刊紹介「人文書」
斜め論: 空間の病理学

| 出版社 | 筑摩書房 |
|---|---|
| 発刊日付 | 2025年8月7日 |
| 著者 | 松本 卓也 |
| 本体価格 | 2,420円(本体2,200円+税) |
| ISBN | 978-4480843333 |
「生き延び」と「当事者」の時代へと至る「心」の議論の変遷を跡付ける。
垂直から水平、そして斜めへ。時代を画する、著者の新たな代表作!
「現代は、ケア論の隆盛に代表されるように、人と人との水平的なつながりの重要性をいうことがスタンダードになった時代である。けれども、単に水平的であればよいわけではない。
水平方向は、人々を水平(よこならび)にしてしまう平準化を導いてしまうからだ。けれども、水平方向には日常を捉え直し、そこからちょっとした垂直方向の突出を可能にする契機もまた伏在している。ゆえに、垂直方向の特権化を批判しつつ、しかし現代的な水平方向の重視に完全に乗るわけでもなく、「斜め」を目指すこと……。
そのような弁証法的な思考を、精神科臨床、心理臨床、当事者研究、制度論的精神療法、ハイデガー、オープンダイアローグ、依存症といったテーマに即して展開したのが本書のすべてである。」
(あとがきより抜粋)
自己実現や乗り越えること、あるいは精神分析による自己の掘り下げを特徴とする「垂直」方向と、自助グループや居場所型デイケアなど、隣人とかかわっていくことを重視する「水平」方向。
20世紀が「垂直」の世紀だとすれば、今世紀は「水平」、そしてそこに「ちょっとした垂直性」を加えた「斜め」へと、パラダイムがシフトしていく時代と言える。
本書は、ビンスワンガー、中井久夫、上野千鶴子、信田さよ子、当事者研究、ガタリ、ウリ、ラカン、ハイデガーらの議論をもとに、精神病理学とそれにかかわる人間観の変遷を跡付け、「斜め」の理論をひらいていこうとする試みである。
著者は、2015年のデビュー作『人はみな妄想する』でラカン像を刷新し、國分功一郎、千葉雅也の両氏に絶賛された気鋭の精神医学者。デビューから10年、新たな代表作がここに誕生する。
おすすめ新刊紹介「理工書」
細胞の分子生物学 原書第7版

| 出版社 | メディカル・サイエンス・インターナショナル |
|---|---|
| 発刊日付 | 2025年7月30日 |
| 著者 | 中村桂子 (監修), 水島昇 (翻訳), 塩見春彦 (翻訳), 三浦正幸 (翻訳), & 1 その他 |
| 本体価格 | 22,000円(税込)(本体20,000円+税) |
| ISBN | 978-4815731311 |
「分子生物学のバイブル」最新版の日本語版が、ついに完成
2025年夏発行・発売予定
●原書初版発行から40年以上もの間、細胞生物学、分子生物学のバイブルとして使用されている教科書。長期間に渡り日本語版がなく、このたび待望の最新日本語版が完成。
●細胞の分子レベルでの仕組みを、平易な文章と1,500点以上の明解な図で示し、原理の説明に加えて重要な遺伝子、分子の名前も具体的に紹介。
●脇に余白を残した一段組レイアウト、段落の中身を具体的に表す説明文のような見出し、統一された美しい図をふんだんに用いて説明、旧版からの特徴的なスタイルを継承。
●細胞生物学の概念的枠組みを身につけ、研究者へのスタートラインに立つための知識を提供、大学院入学試験の出題範囲としても使われる。
●目次立ては旧版を継承しつつも、内容は新たな発見を盛り込み大きくアップデート。約1/4の図版を新規追加または更新。
主な新規の内容は…
・ヒトゲノムやがんゲノムなどゲノム研究による新たな知見
・生体分子凝縮体や、DNAループによる染色体構造など、細胞の構造に関する新しい知見
・機械刺激を感知するピエゾチャネルなど新たに発見された分子に関する知見
・クライオ電子顕微鏡をはじめとする新たな技術による発見
・COVID-19やmRNAワクチンなど,病原体や感染症に対抗する新たな方法
・進化に関する新たな内容:生命の多様性に関する新たな議論、ヒトの進化、HIVの進化
●日本語版は原書の頁と一致するように編集、必要に応じて原文と照合した学習もしやすい。
●旧版から継続された訳者を中心に少人数エキスパートによる翻訳、読みやすく理解しやすい文章を実現。
●学生や若手研究者にも手に取りやすい価格を実現。
●細胞生物学、分子生物学テキストの最高峰として、学生・大学院生・教官・研究者など、それぞれの要望・用途に応えるべく待望の刊行。
クープマン解析: クープマン作用素による非線形ダイナミクスの解析と制御
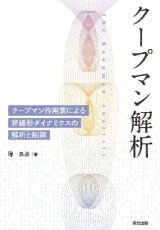
| 出版社 | 森北出版 |
|---|---|
| 発刊日付 | 2025年8月26日 |
| 著者 | 薄良彦 (著) |
| 本体価格 | 4,950円(税込)(本体4,500円+税) |
| ISBN | 978-4627097315 |
機械学習やデータ分析の現場で,いま急速に注目を集める「クープマン作用素」.
状態の変化という複雑なダイナミクスを,観測量の時間発展に落とし込んで解析・制御する考え方であり,理論と応用が同時に発展してきました.
本書は,クープマン作用素の理論から応用までを包括的に説明した,待望の一冊です.
《本書の特長》
●「そもそもクープマン作用素とはどういうものなのか」からていねいに解説.
必要になる数学の知識もわかりやすく説明しているため,高度な数学に抵抗がある人でも安心して読み始めることができます.
●さまざまなダイナミクスに関して,具体例を豊富に掲載.
1行1行の計算を追いかけることで,クープマン作用素の理論を着実に習得することができます.
●具体的な数値計算のアルゴリズムや電力システムの制御に関する,実際の応用事例も紹介.
「クープマン作用素を実際の問題に対してどのように活用するのか」を理解することができます.
非線形最適化法: 数理的基礎とPythonによる実装
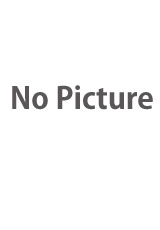
| 出版社 | オーム社 |
|---|---|
| 発刊日付 | 2025年8月26日 |
| 著者 | 成島 康史 (著), 中山 舜民 (著), 矢部 博 (著) |
| 本体価格 | 4,180円(税込)(本体3,800円+税) |
| ISBN | 978-4274233852 |
コンピューター(計算機)の性能向上により計算速度が上がる一方で、計算資源を効率的に利用する必要性も高まっています。本書では、非線形最適化に焦点を当て、そのうちの無制約最適化・制約付き最適化それぞれについて、代表的なアルゴリズムとその収束に関する数理を、丁寧に詳しく解説します。機械学習(人工知能)、情報通信、社会科学などの応用の広がりとともに最適化アルゴリズムの研究は日々進んでいますが、非線形最適化アルゴリズムの数理的基礎は、本書でしっかり足固めできます。
また、本書で扱う最適化アルゴリズムの多くに、Pythonによるサンプルコードを付けており、数理と実装を一挙両得に習得できるよう構成しました。
予備知識として、大学教養レベルの線形代数と微分積分のひととおりの知識を想定していますが、付録で本書の通読に必要な知識をまとめるとともに、本文中ではできるだけ省略なしに数式を展開し、読みやすさにも配慮しています。
Rによる統計データ解析

| 出版社 | 東京大学出版会 |
|---|---|
| 発刊日付 | 2025年8月27日 |
| 著者 | 今野 紀雄 (著) |
| 本体価格 | 小池 祐太 (著), 村田 昇 (著), 吉田 朋広 (著) |
| ISBN | 978-4130629324 |
統計ソフトウェアRを用いて、データサイエンスの基礎である統計学とそれを用いた具体的な統計解析手法・その運用の習得を目指す、統計データ解析テキストの決定版。詳細な数学的知識がなくても、社会人や文系の学生にも役立てられるよう工夫した。
【主要目次】
はじめに
第1章 R の基本的な操作
第2章 データの加工、入出力と整理
第3章 データのプロット
第4章 シミュレーションと極限定理
第5章 確率分布
第6章 点推定
第7章 区間推定
第8章 検定
第9章 分散分析
第10章 回帰分析
第11章 主成分分析
第12章 判別分析
第13章 時系列解析
A 数学的補遺
参考文献
代数的サイクルとエタールコホモロジー 第2版

| 出版社 | 丸善出版 |
|---|---|
| 発刊日付 | 2025年8月4日 |
| 著者 | 斎藤 秀司 (著), 佐藤 周友 (著), 中村 周 (編集), & 1 その他 |
| 本体価格 | 9,680円(税込)(本体8,800円+税) |
| ISBN | 978-4621311677 |
数学ガール/リーマン予想
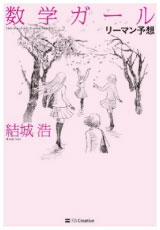
| 出版社 | SBクリエイティブ |
|---|---|
| 発刊日付 | 2025年8月7日 |
| 著者 | 結城 浩 (著) |
| 本体価格 | 2,420円(税込)(本体2,200円+税) |
| ISBN | 978-4815628727 |
高校三年生の冬、「僕」たちの青春は、リーマン予想とともにクライマックスへ――。「僕」と、ミルカさん、テトラちゃん、ユーリ、リサ。五人の仲間を中心に、数学と青春の物語が展開していきます。素数に隠された秘密、それぞれが進んでいく未来、そして「僕」の淡い恋の行方は?
本書は大人気シリーズ『数学ガール』の第7弾にして、最終巻にあたります。本書で「僕」たちが挑む「リーマン予想」は、1859年にドイツの数学者ベルンハルト・リーマンが提示した「ゼータ関数の非自明な零点はすべて実部が1/2である」という予想で、160年以上たった現在も証明されていない、現代数学において最も有名な未解決問題です。
本書『数学ガール/リーマン予想』では、ゼータ関数をめぐる知的な冒険の旅へと、あなたをいざないます。オイラーが見出したゼータ関数が、リーマンによって複素関数へと拡張されて広がった数学の風景は、私たちを魅了し続けています。リーマンが1859年の論文で提示した驚くべき予想を読み解くために、数学ガールたちは素数、複素関数、リーマン面、ガンマ関数、複素積分、解析的整数論といった概念に向き合いながら、学びを進めていきます。そして、最終章ではリーマン予想が書かれた論文に全員で挑みます!
ぜひ、数学ガールたちと「僕」が紡いできた物語の結末を見届けてください。シリーズを愛してくれた読者に、そして「数学って面白い」と感じているすべての人に捧げたい挑戦と発見に満ちた一冊です。
※登場人物や数学的概念などは本作内でていねいに説明していますので、前提知識なしで読み始めることができます。
愉しむ線形代数入門
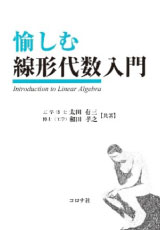
| 出版社 | コロナ社 |
|---|---|
| 発刊日付 | 2025年8月8日 |
| 著者 | 太田 有三 (著), 和田 孝之 (著) |
| 本体価格 | 5,610円(税込)(本体5,100円+税) |
| ISBN | 978-4339061345 |
本書は,大学1年生,高専高学年レベルの知識がある学生を主な読者対象としています。また,一度線形代数を学んだ人にももう一度線形代数を愉しんで勉強してもらうことも目指しています。
【書籍の特徴】
行列式のモヤモヤ、晴らします。
多くの線形代数の教科書では、行列式は「そう定義するもの」として登場します。あるいは、満たしてほしい性質を列挙し、その条件を満たす関数として定義されることもあります。しかし、どちらの場合もなぜそのような定義になるのかということは明示されておりません。
本書では、そうした“天下り式”の説明に頼ることなく、初等的なアプローチを用いて連立一次方程式に唯一解が存在する必要十分条件から行列式を自然に導き出しています。行列式以外の概念についても、定義や定理の前にその必要性や動機を丁寧に解説し、納得しながら読み進められる構成を心がけています。
また、個々の問題や例題にとどまらず、それらの相互関係や共通する構造に意識を向けることで、読者が自分の頭で考え、学びを深める力を育むことを重視しています。愉しみながら効率よく学び、「考える線形代数」を身につけてもらう――それが本書の願いです。
独習書として、あるいは定義に疑問を感じて立ち止まったときのリファレンスとしても最適な一冊です。
多変数の微分積分リアル入門: ベクトル解析と考える

| 出版社 | 裳華房 |
|---|---|
| 発刊日付 | 2025年8月29日 |
| 著者 | 髙橋 秀慈 (著) |
| 本体価格 | 3,960円(税込)(本体3,600円+税) |
| ISBN | 978-4785316082 |
より多くの読者がすこしでも無理なく学習を始められるよう、いきなり数学の厳密な理論を述べることはせず、まずは直観的にとらえやすく、イメージのしやすい内容から説き起こし、ベクトル解析の直観的理解が、多変数の微分積分の理論的理解へとつながるよう、記述に多くの工夫を凝らした。
数学を志すかたはもとより、道具としての数学を必要とする読者にもおすすめの一冊。
曲面のトポロジー
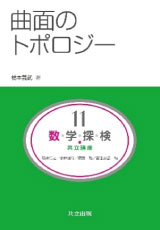
| 出版社 | 共立出版 |
|---|---|
| 発刊日付 | 2025年8月12日 |
| 著者 | 橋本 義武 (著), 新井 仁之 (編集), 小林 俊行 (編集), & 2 その他 |
| 本体価格 | 3,300円(税込)(本体3,000円+税) |
| ISBN | 978-4320111844 |
「ちくわの端と端をくっつけると穴が2つになる」
という発見をした子どもが、その興奮をお母さんに伝えるにはどうしたらよいでしょうか。「穴」とは正確に言うと何なのか、「2つ」とは何をどうやって数えているのか、2つの穴の関係はどうなっているのか、そういうことを「伝わる言葉」にしなければなりません。そのような言葉を与えてくれるのがトポロジーという数学の分野です。
本書ではまず、曲面とその上の曲線や、点と点を線でつないでできる図形(グラフ)のような「見える」図形を、トポロジーの観点から調べていきます。図形の一部をくっつけたり切り離したりすると、「見えない」図形も出てきます。「見える」図形の世界と「見えない」図形の世界は、「くっつけたり切り離したり」を言い直す言葉―位相空間の言葉―によってつながっています。こうして私たちは「見えない」図形たちの待つ広大な未知の世界へと出発することができます。
そして、「見えない」図形の特徴を捉えようとするとき、群の概念から力をもらいます。「図形の特徴を群の言葉で表すということ」もまた数学の対象に他ならず、それを圏の言葉によって語ることができます。そこまで歩みを進めたとき、冒頭の子どもの発見を
「トーラスの1次ホモロジー群はランク2の自由アーベル群である」
と言い直し、さらに2つの穴の関係を双対性の概念を用いて伝えられるようになっているのです。
新装版 大学院への代数学演習
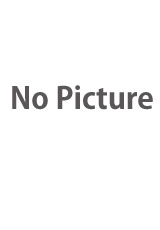
| 出版社 | 現代数学社 |
|---|---|
| 発刊日付 | 2025年8月21日 |
| 著者 | 永田 雅宜 (著) |
| 本体価格 | 3,300円(税込)(本体3,000円+税) |
| ISBN | 978-4768706749 |
実験計画法の基本: 統計的取扱いと原理
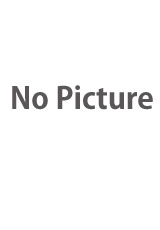
| 出版社 | サイエンス社 |
|---|---|
| 発刊日付 | 2025年8月20日 |
| 著者 | 山田 秀 (著) |
| 本体価格 | 3,630円(税込)(本体3,300円+税) |
| ISBN | 978-4781916422 |
【主要目次】データ収集と解析により因果を推定する実験計画法/1因子の要因計画とそのデータ解析/2因子の要因計画とそのデータ解析/多因子の要因計画とそのデータ解析/2水準直交表による一部実施要因計画/種々の一部実施要因計画/一部実施要因計画の基礎理論/ブロック因子を導入する計画/分割計画/パラメータ設計/最小2乗法によるデータ解析とその行列表現/応答曲面推定のための計画/応答曲面の解析法/最適計画/コンピュータ実験の計画と解析
数理経済学の稜線 第1巻 マクロ動学・ゲーム理論の基本モデル
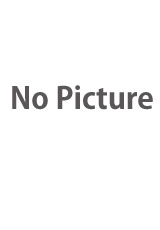
| 出版社 | 現代数学社 |
|---|---|
| 発刊日付 | 2025年8月21日 |
| 著者 | 中村 勝之 (著) |
| 本体価格 | 3,410円(税込)(本体3,100円+税) |
| ISBN | 978-4768706732 |
フィボナッチ数・リュカ数大鑑(上)

| 出版社 | 共立出版 |
|---|---|
| 発刊日付 | 2025年8月27日 |
| 著者 | Thomas Koshy (著), 青木 美穂 (翻訳), & 8 その他 |
| 本体価格 | 16,500円(税込)(本体15,000円+税) |
| ISBN | 978-4320115880 |
フィボナッチ数とリュカ数は定義が明快であることから、あらゆる領域での応用がみられる。その研究は数学だけにとどまらず、日常生活の中や、自然科学の諸分野、芸術にいたるまで多岐にわたるが、それゆえに各分野での研究成果が散逸した状態にあった。本書では、きわめて膨大なそれらトピックについて、昔の稀覯本から最新の研究論文まで可能な限り網羅し、詳細な議論を行なっている。フィボナッチ数とリュカ数をめぐる人類の叡智の結晶ともいえる書籍である。
上巻では、まずはフィボナッチ数とリュカ数の定義から始める。その後、花びらの数や種の螺旋模様、絵画の構図、古代の建造物の比率などといった、自然や生活の中に潜むフィボナッチ数・リュカ数を追究する。その後は下巻への大きな進展を見据えて、黄金比、タイリング、行列式、グラフ理論、組合せ論などの議論を進める。
また本書では、フィボナッチ数とリュカ数の発展に関する歴史的な調査も含まれている。各分野での重要人物の伝記的なスケッチや文献を加えることで、歴史的研究への便宜を図るとともに、「魅力的な数」をめぐる物語に躍動感を与えることを試みた。
各章には、豊富な例題と、繁雑な定理の証明を避けるための数値的・理論的な演習問題を掲載した。パターン認識、推測、証明技術の応用など問題解決へのさまざまなスキルやテクニックを説明し、さらに発展的な内容へ取り組むための足固めとなる準備も進める。
本書は、数学史、組合せ論、整数論に関する高学年および大学院レベルのコースに適している。また、コンピュータ科学者、物理学者、生物学者、電気工学者にとっても有益な資料であり、学部の研究コース、自主研究プロジェクト、卒業論文などにも利用できる。
フィボナッチ数・リュカ数大鑑(下)

| 出版社 | 共立出版 |
|---|---|
| 発刊日付 | 2025年8月12日 |
| 著者 | Thomas Koshy (著), 小松 尚夫 (翻訳) |
| 本体価格 | 16,500円(税込)(本体15,000円+税) |
| ISBN | 978-4320115897 |
下巻にあたる本書では、上巻で身に着けたパターン認識、推測、証明技術の応用などのスキルやテクニックを駆使し、フィボナッチ数・リュカ数に関する議論を更に発展させていく。
本書では、フィボナッチ、リュカ、ペル、ペル-リュカ、ヤコブスタール、ヤコブスタール-リュカ、ヴィエタ、ヴィエタ-リュカ、チェビシェフ多項式を含む、拡張ギボナッチ族への発展的なアプローチの紹介を最終的な目標としている。
上巻に引き続き、歴史的な調査についても引き続き加えることで「魅惑的な数」の壮大な物語に躍動感を与えている。
本書では、フィボナッチ数・リュカ数研究の中でも、ここ100年以内で発表されたような比較的新しい内容が数多く取り上げられており、全体として魅力的で独創的なアプローチがとられている。
学部上級生や大学院生、自主研究チームによる共同研究やグループディスカッション、セミナー、プレゼンテーションのための題材ともなり得る内容も豊富に用意されており、本書で扱われているトピックは、きっと知的好奇心、創造性、創意工夫を搔き立ててくれるだろう。
また、学部生、大学院生の論文執筆にとっても貴重な資料となるだろう。数学を初めとする全ての自然科学系の専門家だけでなく、好奇心旺盛なアマチュアにとっても歓迎すべき一冊である。
分子性導体: 物理学と化学との連携がもたらすπ電子物性科学 (物質・材料テキストシリーズ)

| 出版社 | 内田老鶴圃 |
|---|---|
| 発刊日付 | 2025年8月4日 |
| 著者 | 加藤礼三 (著) |
| 本体価格 | 4,950円(税込)(本体4,500円+税) |
| ISBN | 978-4753623259 |
凝縮系における場の量子論: 初歩からはじめるファインマンダイアグラム

| 出版社 | 共立出版 |
|---|---|
| 発刊日付 | 2025年8月26日 |
| 著者 | 田島 裕之 (著), 加藤 岳生 (監修) |
| 本体価格 | 3,850円(税込)(本体3,500円+税) |
| ISBN | 978-4320036376 |
本書の特徴は、ファインマンダイアグラムの応用例として冷却原子気体のような比較的最近の話題を取り上げている点である。多くの量子多体系の教科書の序盤では、理想フェルミ気体や理想ボース気体が取り上げられているが、冷却原子気体では実際にこうした“理想的な系”を実現しうる。さらに、粒子間の相互作用が強くなったらこうした気体はどうなるのかという基本的な問いにも実験的に調べられるようになった。ファインマンダイアグラムは、この相互作用効果を取り扱うものである。
強相関系の量子多体問題を理解するのに、発現機構のコンセンサスが取れないほどに複雑な高温超伝導を例題として提示するのはやはり難しい。なるべくシンプルな系に立ち返るという意味で、冷却原子気体はまさに理想的な系であるといえる。物理学を学ぶのにあたり必ずしも人類が見つけた順に学ぶのが適切とは限らない。伝統的な良書が多い量子多体物理において、昨今の進展を反映した新しいスタイルの教科書があってもよいのでは、という思いを胸に本書を執筆した。(本書「まえがき」より)
宇宙のアノマリーはどこまで判明したのか 標準モデルを揺るがす謎の現象
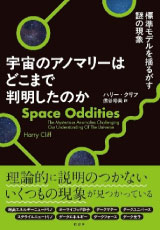
| 出版社 | 柏書房 |
|---|---|
| 発刊日付 | 2025年8月13日 |
| 著者 | ハリー クリフ (著), 熊谷 玲美 (翻訳) |
| 本体価格 | 2,860円(税込)(本体2,600円+税) |
| ISBN | 978-4760156375 |
これまで物理学は先に理論を打ち立て、それを実験によって確かめるという方法を取ってきた。ヒッグス粒子の発見はそうした流れにおける象徴的な出来事で、これによって標準モデルという理論の正しさが確認されたのだ。そしてこれですべてが解明された(ニュートンの時代も同様)と思わずにはいられなかった。しかし、本当にそうだろうか? と考える物理学者が出てきた。そして徐々に実験精度が高まり、また大規模な実験が出来るようになり、これまでの「標準モデル」から逸脱する実験結果がたくさん見つかるようにもなってきた。そのため実験結果から理論を見直すという方向に変化してきてもいる。つまり、アインシュタインによる一大転換からさらに新しい物理学を探そう、という方向に向かっているのだ。本書はその現状とこれまでの経過を前作と同様、研究者へのインタビューも含め、わかりやすく面白く書きまとめた読み物となっている。さて、新しい物理学は見つかるのだろうか。
XAFSの基礎と応用 第2版 (KS物理専門書)
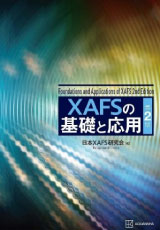
| 出版社 | 講談社 |
|---|---|
| 発刊日付 | 2025年8月29日 |
| 著者 | 日本XAFS研究会 (編集) |
| 本体価格 | 5,060円(税込)(本体4,600円+税) |
| ISBN | 978-4065404867 |
XAFSの理論・解析法はもちろん、放射光を利用した測定系、時間・空間分解測定や発展的手法までを、第一線の研究者がて
いねいに解説。XAFSのすべてがわかる。研究者必携の一冊!
配位子場理論 錯体物性科学への応用 (KS化学専門書)
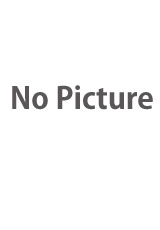
| 出版社 | 講談社 |
|---|---|
| 発刊日付 | 2025年8月29日 |
| 著者 | 小島 憲道 (著), 渡邉 直寛 (著) |
| 本体価格 | 6,270円(税込)(本体5,700円+税) |
| ISBN | 978-4065390320 |
遷移金属錯体を中心とする分子集合体は、金属イオンの多彩な光学的性質や磁気的性質、配位子のもつ次元性の制御機能など、無機物質および有機物質の優れた特徴を兼ね備えている物質群であり、物性現象の宝庫である.本書は、このような魅力ある物性現象について配位子場理論を応用して解き明かすことを目的としている。
本書は 14章と 3 項目の付録で構成されており、前半では配位子場理論とその解析法を述べ、3d電子系の田辺・菅野準位図を読者自ら作成できるよう心掛けた。後半では、金属イオン間に働く様々な磁気相互作用と磁気相転移および光学遷移、スピンクロスオーバー現象や多核金属錯体の超常磁性や単分子磁石、混合原子価錯体で現れる光誘起磁性や光誘起原子価転移、発光現象とその応用について述べた。
細胞膜: 膜と膜タンパク質の生化学

| 出版社 | 共立出版 |
|---|---|
| 発刊日付 | 2025年8月27日 |
| 著者 | Stephen H White (著), Gunnar von Heijne (著), & 4 その他 |
| 本体価格 | 13,200円(税込)(本体12,000円+税) |
| ISBN | 978-4320058477 |
本書の中心テーマは、細胞膜の構造的および組織的原理と、それらの原理がどのように機能を可能にしているかである。本書は、脂質二重層の組織化や膜タンパク質の折れたたみ、組み立て、安定性、機能についての生物学的および生物物理学的な基盤を構築することを目的としている。これにより、生物科学を学ぶ学生が、膜に関する基本的な物理学や物理化学の知識を深められるようにすることを狙っている。同時に、物理学の学生にとっても親しみやすい内容となるように構成されており、生物学への関心を引き出すことが期待される。細胞膜や膜タンパク質の理解は、生物学と物理学の両方を組み合わせたアプローチが不可欠である。本書では、現在私たちが知っていることだけでなく、それがどのように解明されてきたのかについても重視している。そのため、特に序盤の章では、後の内容の基礎となる重要な発見の歴史を紹介する。
生命科学の理解に欠かせない熱力学から始める(第0章)。第1章~第4章では、生体膜、脂質二重層、ペプチド・タンパク質と脂質二重層との相互作用を扱う。重要な概念については、その起源をたどりながら話を進める。第5章~第7章では、分子細胞生物学の視点から膜を観察する。タンパク質はどのようにして細胞膜を横切るか、また膜成分間を移動するか、膜タンパク質はどのように合成され、いろいろな種類の膜に挿入されるのか、タンパク質は細胞膜の形成にどのように役立つか。これらの現象のいくつかをタンパク質と脂質の相互作用の基礎となる物理学に関連づけることができるか、などの問題を取り上げる。後半の第8章~第15章では構造決定法入門と、膜タンパク質の最重要メンバーであるチャネル、トランスポータ(輸送タンパク質)、生物エネルギー論で活躍するタンパク質の巨大複合体、シグナル伝達に関わる細胞表面レポータを扱う。
本書により生命科学の今後の発展を期待し、さらに読者自身がこの魅力ある学問を支え、発展させようとの気持ちを持つよう鼓舞してくれることを期待する。
イカの恋、タコの愛 (岩波科学ライブラリー 336)

| 出版社 | 岩波書店 |
|---|---|
| 発刊日付 | 2025年8月22日 |
| 著者 | 佐藤 成祥 (著) |
| 本体価格 | 1,980円(税込)(本体1,800円+税) |
| ISBN | 978-4000297363 |
原論文から解き明かす生成AI 単行本(ソフトカバー)
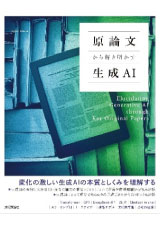
| 出版社 | 技術評論社 |
|---|---|
| 発刊日付 | 2025年8月18日 |
| 著者 | 菊田 遥平 (著) |
| 本体価格 | 3,300円(税込)(本体3,000円+税) |
| ISBN | 978-4297150785 |
生成AI技術は目覚ましい進歩を続けています。そのため、表面的なトレンドを追うだけでは、そのしくみを理解することが困難になっています。本書は、このような状況を受けて、生成AIを支える理論的基礎について原論文レベルまで深く踏み込んで解説し、読者が技術の核心部分を理解できるよう導く一冊です。本書の主な特徴は、以下の3つにあります。
1つ目の特徴は、Transformerから推論時のスケーリング則に至るまでの「生成AIの重要な理論」について、原論文の内容を参照しながら数式と図版を用いて詳細に解説しています。2つ目の特徴は、英語・日本語を問わず既存の文献ではあまり扱われていない分布仮説の実験的根拠や拡散モデルの数学的保証など、「生成AIを理解する上で、重要であるものの他の書籍などで十分に扱われていない理論」も丁寧に掘り下げています。3つ目の特徴として、「演習問題とGitHubサポートページを連携させた読者参加型の学習環境」を提供し、より深い学びをサポートしています。
本書を通じて読者は、生成AIに関わる重要な理論について深い理解を得ることができるだけでなく、原論文レベルの内容を読み解く力を身につけることができます。これにより、新たなモデルや技術動向を独力で理解し、急速に変化する技術トレンドへの自律的なキャッチアップ能力を獲得することができるでしょう。表面的な知識ではなく、生成AI技術の本質的な理解を求める全ての方にとって、必携の一冊です!
ChatGPT科学英語論文作成術
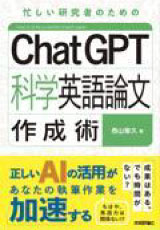
| 出版社 | 技術評論社 |
|---|---|
| 発刊日付 | 2025年8月18日 |
| 著者 | 西山聖久 |
| 本体価格 | 2,640円(税込)(本体2,400円+税) |
| ISBN | 978-4297150662 |
本書は、AIを活用して効率的かつ効果的に科学技術英語論文を書き上げるための実践的なガイドです。
英語での論文作成に苦労していませんか?
ChatGPTをあなたの研究室の強力なアシスタントに変え、論文執筆の新たな扉を開きましょう。本書を読めば、構成の理解から具体的な執筆方法、そしてAI利用の注意点まで、英語論文を完成させるための全てが手に入ります。
さあ、あなたもChatGPTと共に、研究成果を世界へ発信しませんか?
基盤モデルとロボットの融合 マルチモーダルAIでロボットはどう変わるのか (KS理工学専門書)

| 出版社 | 講談社 |
|---|---|
| 発刊日付 | 2025年8月29日 |
| 著者 | 河原塚 健人 (著), 松嶋 達也 (著) |
| 本体価格 | 3,630円(税込)(本体3,300円+税) |
| ISBN | 978-4065395851 |
これまでのロボットには困難だったタスクにどう挑むのか。
「フィジカルAI時代」の中核技術を理解するための指針となる一冊。
★★生成AIによる大変革、次の主役はロボット!★★
■ロボットを知らなくても読める!
この大変革の流れを知らずして、AI・情報科学の未来は語れません。
AIに関心のある研究者、エンジニア、マネージャー、起業家――
技術の潮目をつかみたいすべての人に贈ります。
■AIが“世界に接する”時代へ!
生成AIは、いまや言語や画像にとどまりません。
LLMを超え、より大規模でマルチモーダルなモデルが「基盤モデル」です。
それがロボットと結びつき、世界に接するAIが生まれています。
・「あれ取ってきて」という指示に応答するロボット
・みずからコードを書いて自分を制御するロボット
・未知の環境でも、試行錯誤して成果を出すロボット
かつてできなかったことが、基盤モデルの力で実現しています。
■語り尽くすのは、最前線を走る若きツートップの研究者!
「そもそも、基盤モデルとは何なのか?」
「基盤モデルでロボットの何が変わるのか?」
「基盤モデルをロボットにどう使うのか?」
技術の本質を捉えたい人に向けて、深く・わかりやすく語り尽くします。